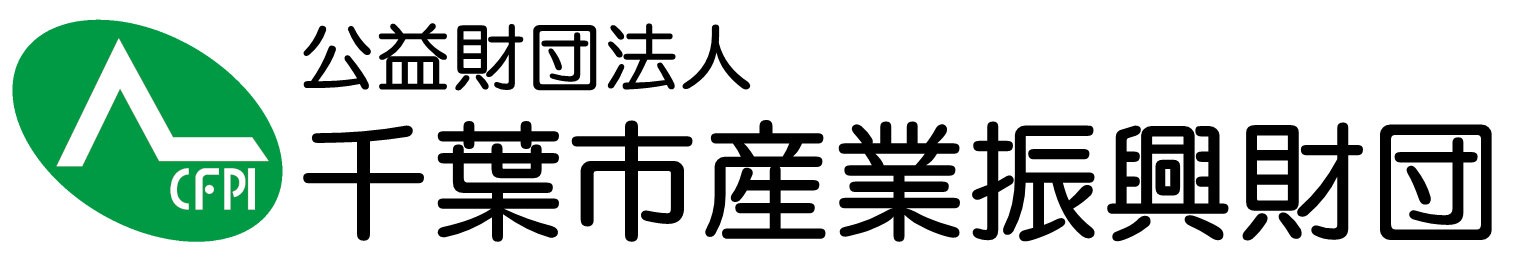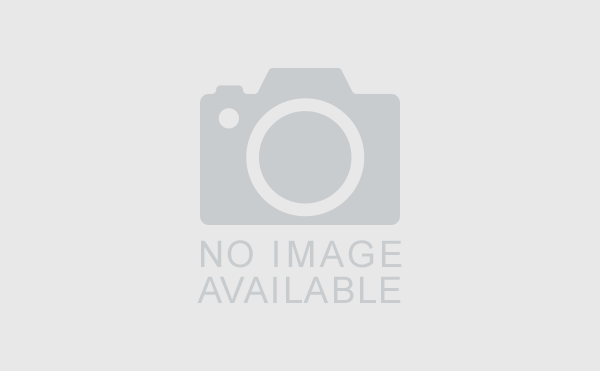会社概要
| 会社名 | 株式会社オーエックスエンジニアリング |
|---|---|
| 代表取締役会長 | 石井 勝之 |
| 所在地 | 千葉市若葉区中田町2186-1 |
| 設立 | 1988年10月 |
| 資本金 | 7,500万円 |
| 社員数 | 33人(グループ全体70)(2024年3月時点) |
| 事業内容 | 車いすの開発・販売 |
| HP | https://www.oxgroup.co.jp/ |
支援内容
- 活用した支援
- ・経営、技術(コーディネーター)相談
・産学共同研究促進支援
・ビジネスシーズ交流会
・ICT活用生産性向上支援 等
- 効果
- ・生産性の向上
・車いすオーダーシステムの構築と
販売・会計システムの連携
・オーダーから製造・在庫管理までの
一元管理システムの連携
- 課題
- ・生産性の低さ、長時間かつ経験に依存した採寸作業
⇒抜本的なデジタル変革(DX)
- 解決策
- ・ICT導入支援(費用の一部助成)
・産学連携支援(費用の一部助成)
・各種申請サポート(無料) 等
長期にわたる包括的な伴走支援で構造改革中!業界の未来を見据えた施策。
千葉市若葉区に本社を構える株式会社オーエックスエンジニアリングは、車いすの開発・製造・販売・メンテナンスを手掛けています。パラリンピックで4個の金メダルを獲得し、国民栄誉賞を受賞した国枝慎吾さんなど、パラスポーツ界をけん引するプレーヤーが愛用する車いすメーカーとして、国内外で高い知名度を誇ります。
1992年に初のオーエックスブランドの車いすを販売して以降、現在は30モデル以上を展開しています。200店ほどの福祉機器販売店で取扱いがあり、事業を拡大し続けていました。
しかし、製造業につきものの課題は、同社も例外ではなかったのです。
-千葉市産業振興財団の支援を受けたキッカケを教えてください。
創業者である父の代から、千葉市産業振興財団(以下「財団」という。)には助成金などでお世話になっていたようです。継続的な支援を受けるようになったのは、私が代表に就任した2013年ごろからです。
当社はおかげさまで知名度はある方なのですが、知名度が利益に直結しているかというと、そうではありませんでした。
理由は、生産性の低さ。当社製品は基本的にオーダーメイドなので、お客様の体格や性別、障害の特徴を見極めて、普段どのような生活をしていて、車いすにどのような機能を求めるのかをヒアリングしながら採寸していかなくてはなりません。そのため、採寸する人に専門知識が必要です。ヒアリングと採寸で平均して2時間かかるため、お客様を長時間拘束してしまうことも課題でした。
また、採寸を行う街の福祉機器販売店には、少子高齢化における後継者問題もあります。縮小していく業界で、どのように販売経路を確保していくかも同時に検討していく必要があったのです。
さらに、販売から製造・納品までのプロセスがすべて人の手によって行われていました。具体的には、採寸・ヒアリング、注文や受注処理、製造工程の生産指示や在庫確認をすべて手作業で行っており、担当者の経験に頼ったビジネスモデルでした。
我々のモノづくりに対するこだわりは残しつつ、時代に即したやり方に変えていかなければならないという危機感がありました。しかし、最終的なイメージ像はあっても、それを具現化する術は私の中にはありませんでした。
そこで、日ごろからお世話になっていた財団に相談し、長期にわたるコーディネーター支援により、現在に至るまで構造改革を実行中です。

行政系の機関だからこその中立性。俯瞰した目線での提案。
-具体的にどのようなステップで進めていったのですか?
まずは、現状を整理するところからスタートしました。生産性を上げなければならないのはわかっていたので、具体的にどこから着手していこうか、一つずつ紐解いていく必要がありました。コーディネーターと膝を突き合わせて話をするうちに、販売現場の課題、生産現場の課題、全体を通した課題が少しずつ明確になっていきました。
当社の場合は、大きな課題が主に3つありました。1つ目は、先ほど申し上げた販売から生産工程まですべて人の手を介していること、2つ目は採寸やヒアリングの専門家・技術者の育成に時間がかかることから受注の機会を逃してしまっていること、そして3つ目は販売側と生産側、そして請求システムが連動しておらず、無駄な作業が発生していることです。
1つ目と2つ目は、属人化していることが原因で、3つ目は、各工程が独立してしまっていることが原因です。この課題すべてを解決する方法が、入口から出口まで一貫したシステムをつくる、ということでした。これを実現するために、さまざまな手段を使って少しずつ改革を進めていって、8年目になりました。(※2024年3月時点)
-これまでに、どのような支援を受けてきましたか。
たくさんありますよ(笑)。産学共同研究促進支援、ビジネスシーズ交流会(デザイン経営-課題解決のためのデザイン)、新規市場開拓支援、元気企業認定、ICT活用生産性向上支援、コーディネーター支援…。変化の激しい時代ですから、日々テーマが変わります。私は業界や自社のことはわかりますが、世の中全体や別の業界に関することを知るには限界があります。財団はさまざまな業界の事業者支援をしていますから、今の世の中の流れを加味して俯瞰的にご指導いただけるのはありがたいですね。
また、補助金申請に関する事業計画の書き方なども、「この方が伝わりやすい。ここは書き方にコツがいる。」と、親身になってアドバイスをいただいています。行政系の書類は言い回しが独特というか、自社内で完成するには労力がいるじゃないですか。民間の外部コンサルタントだと利益ありきなので、補助金の獲得がゴールになりがちですが、財団は企業の自立支援を目的としている団体ですから、自社内に書類作成のノウハウが溜まっていく実感があります。

産学共同研究で大学の知見を生かしたシステム構築。春の展示会で披露できる段階へ。
-入口から出口まで一貫したシステムを作るために、大学との連携もされています。
はい、「ビジネスシーズ交流会」という大学等の研究機関の知見を生かし、実際の中小企業の課題をデザインで解決するという活動に参加させていただきました。現在、千葉工業大学の研究室と一緒に販売工程でのシステム構築を進めています。
販売工程、つまりヒアリング・採寸から受注処理をシステム化するにあたり最大の課題は、ヒアリング・採寸に専門家の暗黙知が集中していることでした。そこで、共同研究の一年目は当社で実際に活躍しているベテランを「プロ」とし、知識も経験もない人を「初心者」として、実際に採寸・ヒアリングをしてもらい、具体的にどのプロセスで暗黙知が必要なのかを可視化していきました。
プロと初心者の採寸を比較した結果、「採寸項目の数値を決定する時の判断基準」と「部品に関する知識」に差があることがわかり、さらに採寸をする際にカタログの情報だけでは不十分なことが判明しました。ここが、測定者を専門家とさせている要因だったのです。
そこで、部品の情報はもちろん、必要な情報を入力すれば自動的に数値が表示されるようなテンプレートを作成し、採寸者のレベルに頼らず、必要項目を選択していくだけで注文書が完成するシステムを開発することに成功しました。採寸・ヒアリングの時間は、2時間から30分に短縮できる想定です。
現在、フラグシップモデルへの実装が完了し、今春の展示会で披露できる予定です。今後は、今回のシステムが他のモデルに適応できるのかの検証を行い、最終的には全モデルでシステムが利用できるようにしていきたいと考えています。実現すれば、当社はもちろん、代理店の生産性も劇的に向上します。

採寸から在庫管理までワンストップを実現。これからも財団とともに改革を実行。
-販売工程のシステム構築はほぼ完了しているとのことですが、生産工程の方はいかがですか。
生産工程のシステム自体は、もともと内製で作ったものがあったのですが、ICT活用生産性向上支援を受けてプロの目線で再構築を行いました。販売工程のシステム構築と並行して進めており、こちらも9割ほど完成しています。
ICTに関しても、コーディネーターと週1、2回の面談を行い、ベンダーの選定から慎重に行っていきました。システムって物がないんですよね。一つ間違えば、何千万円もかけたにも関わらず、自社の役に立たないシステムが出来上がってしまう可能性があります。私たちから見ると、そのシステムが適正な価格なのか、私たちが求めているものに本当に必要な機能なのかの判断がつかないのですが、システム開発側の知見のあるコーディネーターに入っていただいたおかげで、ベンダーとの交渉などもスムーズに行うことができました。
また、販売工程のシステムと生産工程のシステムを連結させる開発も行っており、これが実現すれば採寸から納品までがワンストップになり、人の手が介在していたプロセスはおおむねデジタルで対応できるようになります。システムの実装自体はほぼ終わっているので、今後は、2、3年をかけて社内や販売代理店などに浸透させていければと思っています。
最終的には、デジタルの力を使ってお客様に楽しんで車いす選びをしてもらいたいですね。効率化により発生した時間を使って、人間にしかできないことをしていくことで、サービス品質を向上させ、利益率を上げ、結果的に従業員に還元できるような仕組みづくりができればと思っています。
また、少子化待ったなしの日本で、海外展開は避けては通れない道です。現在は海外の代理店は数店にとどまっていますが、システム化を期に海外市場も拡大していく予定です。
-最後に、財団にこれからも支援して欲しいことなどがあれば教えてください。
そうですね、こんなに長期的なお付き合いをさせていただき、抜本的な改革をしていけるとは想像していなかったので、とても感謝しています。強いて言えば、研修事業の対象者拡大ですかね。現在は経営者向けのセミナーが主だと思うので、新入社員向けの研修や、クラウドやシステムなど一つのテーマに特化したセミナーなどがあれば、利用したい企業も多いのではと思います。
当社の支援に関しては、8年目でまだまだ道半ば、という段階なので、引き続き伴走支援をお願いしていきたいです。

-ご協力ありがとうございました。
取材協力:株式会社キウ(Kiu)